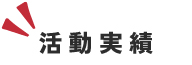多種多様の個性は無限の可能性!
『為せば成る、為さねば成らぬ何事も。成らぬは人の為さぬなりけり。』
自分だったらどうする?
5年後の私たちの街、どうなってる?
考える、そして実行する。みんなも、私も。
そんな地域政治を一緒につくっていきませんか?
12月定例県議会では、「千葉県公文書等の管理に関する条例の制定に関する請願書」が採択されました。その紹介議員として考えを述べさせていただきます。
今回の請願は、現場に精通した方を含めて、専門家の立場で公文書の重要性を訴える、歴史学、アーカイブ学、文化財学などの大学教授や研究者28名からのものでした。
まず、公文書は、行政組織としての利用などに留まらず、広く県民の財産です。
その中でも、歴史的な価値を有する公文書は、後の世代が、過去の重要な政策決定を参考に、その時代の課題解決をするために有用であり、また、過去の歴史や文化等を振り返るうえでも、その当時を知ることが出来る大変貴重な資料となります。
千葉県では、過去の公文書の誤廃棄や所在不明となった事案を受けて対策を進めているところであり、私が担当した6月議会の党代表質問においても、「所在不明の事態を防ぐ仕組み作りと、職員の周知徹底、特に、県の電子決裁率が8割を超えており、行政文書の電子化が急速に進んでいる今の流れを踏まえて、デジタル技術を活用した仕組みの構築」を求めたところでしたが、改めて、職員一人一人が公文書の重要性を認識したうえで、適切に扱う意識の更なる醸成を図り、デジタル技術等を活用した仕組みの構築を法的ルールにより推進していく必要があります。
議員発議による条例制定も選択肢にはありましたが、公文書等の管理に関する法律の制定(平成21年)の前から、各都道府県で各々に行われてきた公文書管理の運用実体の違いや専門技術的な事項を踏まえると、制定後の現場運用を含む調整など、策定作業が複雑・多岐に及ぶため長期間を要し、公文書に係る専門性も求められることが想定されることから、執行部側に条例案の策定を求めることが良いと判断しました。
また、公文書管理の条例を制定することは、そもそも作成すべき公文書についても、改めて、法的規律による観点からの整理をしていくことを意味します。
この点については、政策や施策(事業)決定の判断にあたっての、理由やデータ分析等の検討状況を、きちんとルールに則って公文書に記録することにより、将来世代が、時の為政者の判断を客観的・中立的記録を通して検証できる点で極めて大きい意義を有すると考えています。
というのも、我々のような政治家が発信するホームページやSNSなどは、後からでも編集・変更ができてしまいますので、職務の中立性が強く求められている公務員だからこそ、ここの法的ルール化と規律は大事だと思うのです。
相応の時間を要すると思いますが、条例の制定に向けて議会側における協力に努めてまいります。